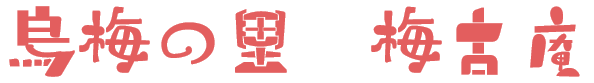2025/08/09 20:08

奈良市役所ホームページに烏梅コーラ開発物語が掲載されました。以下一部抜粋
見慣れない黒いかたまり。これは、烏梅(うばい)といいます。今から約1300年前に、遣隋使が薬として日本に伝えたものです。
完熟した梅の実を炭粉で覆い、地中の窯で燻蒸(くんじょう)し、天日で乾燥させる。この製法は、今日まで受け継がれています。烏梅は薬に加え、衣類の紅花染めや口紅の媒染剤として広まっていきました。
その烏梅の一大産地となったのが、奈良市月ヶ瀬(つきがせ)地区でした。
「月ヶ瀬には10万本の梅が植えられ、最盛期には400軒もの烏梅生産所があったといわれます。しかし、明治時代に入ると化学染料が広く普及。烏梅の需要はみるみる減少していきました。戦後、奈良市で烏梅づくりを営む最後の一軒となったのが梅古庵でした」
そういって迎えてくれたのは、梅古庵の10代目にあたる中西謙介さん。
幼少期から烏梅づくりを手伝ってきました。学校卒業後は、群馬県で就職。15年間ほど自動車関連の仕事につきました。この間も、毎年6月から7月にかけては奈良へ戻り、烏梅づくりを手伝ってきました。奈良へ帰り、家業を継いだのが2018年のことでした。
課題:烏梅をtoBからtoCへ
国選定保存技術「烏梅製造」を保有する梅古庵は、1300年変わらぬ伝統製法で烏梅を製造しています。それほど貴重な技術がありながらも、産業としては成り立っていませんでした。
「2018年当時の生産量は、年間40キロほど。京都、東京、山形などで染業を行う数軒の取引先に細々と出荷するのみでした。しかし、烏梅にはもっと可能性があると思いました」
では、どのように生計を立て、烏梅の文化を継承させてきたのでしょうか?
梅古庵は、月ヶ瀬でお土産販売店とレストランを営んでいます。そのため中西さんは調理師免許も所有。こうしたバックグランドを活かして“烏梅のキュレーター”となり、BtoBからBtoCへと烏梅の用途を広げることに取り組んだのです。
中国や台湾で親しまれている薬膳茶の酸梅湯(さんめいたん)、そして薬膳料理としての提供。また、紅花染めの教室を開催します。こうした取り組みには、女性を中心とする反響がありました。用途拡大に伴い、烏梅の生産量も2018年に比べて4倍以上へと増えています。
挑戦:烏梅をクラフトコーラに?
梅古庵が新たな挑戦として描いたのは“烏梅コーラ”の開発でした。
「ぼく自身、クラフトコーラがすきなんです。だから烏梅を原料にしたクラフトコーラをつくりたくなった。はじめは外注による委託生産を検討していました。でも最小ロット数が大きく、コストも高くなってしまう。そこで自由度の高い自社生産へと踏み出します」
梅古庵には、すでに梅干しなどを製造する漬物加工場がありました。保健所へ確認を行うと、加工場の部分改修を行い、清涼飲料水の製造許可を取得できる見込みがありました。結果として改修、商品開発、商品デザイン、通信販売にかかる初期投資は100万円ほどに収まりました。その一部に「奈良市中小企業等新たな挑戦支援補助金」を活用したのです。
「レシピ開発も自分で取り組んでいきました。烏梅に加えて、生梅も加えることでフルーティな味わいになります。烏梅と相性のよい紅花を加えよう。コーラの語源となったコーラナッツをはじめ、いろいろなスパイスを組み合わせよう。砂糖は、黒糖のほうがよさそう。そうして試作を進めていき、烏梅コーラが完成しました」
まずは梅古庵や県内外のマルシェで、開発したシロップをソーダで割るところから提供をはじめていきました。お客さんに知ってもらいつつ、感想を得ることで、味の改良を重ねていきます。そこで発見したのは、これまでは烏梅に縁の薄かった男性に好評であること。ウイスキーを思わせるスモーキーな香りが「とてもおいしい」という感想につながります。また海外の観光客からの反応も得ることで、意外にもヨーロッパ圏の人から好評であることがわかりました。
こうしてスパイスの種類と配合を見直したのち、お土産品の開発も行います。パッケージは袋詰め、缶詰め、瓶詰めを試作した上で、瓶詰めを採用。自社のECサイトに加えて、奈良県内の小売店での委託販売も進めていきます。
梅古庵では「奈良市中小企業等新たな挑戦支援補助金」を活用して、完熟梅シロップ、烏梅エキス入りねり梅も開発しました。
なかでも幅広い客層が手に取るのは、完熟梅シロップです。市場流通しづらい完熟梅を使用することで、まるで梅園にいるかのような梅の香りを味わえる仕上がりになりました。烏梅コーラと並べて販売できるよう、統一感のあるラベルデザインを採用しています。
ねり梅はおにぎり、サラダ、肉料理のアクセントにもおすすめ。こちらは、お客さんの声から生まれた商品です。
「烏梅ドレッシングを開発していたとき、健康志向のお客さんから『油を控えたい』という声がありました。いろいろな食材との相性を探りながら、烏梅エキスと梅干しだけのシンプルなねり梅が完成したんです」
マルシェでのテスト販売が好評だったので、梅古庵にて販売を開始しました。今後はさらに烏梅のソースにも取り組んでいきたいと考えています。
次の挑戦:口紅をつくりたい
用途を広げていくことで、わたしたちの暮らしに烏梅を重ねていく梅古庵。烏梅の需要も、まだまだ増えていきそうです。ちなみに100キロの完熟生梅からつくられるのは、わずか14キロの烏梅なのだとか。機械化による大幅な生産量の増加も期待できそうですが、中西さんはこう言います。
「変わらない製法でつくり続けることに価値があると思います」
梅古庵では、今年も新たな挑戦がはじまろうとしています。
「烏梅は古くから薬、染色、口紅に用いられてきました。この3つをわたしたちの暮らしに重ねたいんです。これまで薬と染色に取り組んできたので、次は口紅をつくれたら」
ここで中西さんが見せてくれたのは、烏梅をもちいて紅花染めをした生地。自然界にある植物から、これほど鮮やかな色が生まれるのです。
烏梅は、口紅の媒染剤としても使われてきました。ちなみに、スティックタイプの口紅が登場したのは明治以降のことだそう。それまでは、口紅といえば筆で塗るものでした。
中西さんは赤膚焼の器、奈良筆、吉野杉の化粧箱といった奈良の工芸を組み合わせた口紅の開発を考案中です。
地域:月ヶ瀬に産業をつくる
インタビューが佳境へと差しかかったところで、外から声が聞こえてきました。
「梅がとれましたよー」
声の主は、月ヶ瀬梅渓保勝会の方。運び込まれたのは、収穫されたばかりの完熟梅でした。
その様子を見に行く中西さんについていきます。
「これが烏梅の原料です。明日から約2か月かけて、烏梅づくりがはじまります」
口紅がひらくのは、烏梅の未来だけではありません。
「口紅をつくる上では、紅花が欠かせません。月ヶ瀬に増えつつある耕作放棄地を活用して、紅花を栽培していけたら。この地域で仕事をつくることにもつながる。だれか、やりたい人はいないかな?」
2018年に奈良へ帰ってきた中西さん。一人がはじめた挑戦は7年目を迎え、地域の挑戦へと広がりつつあります。
(2025年6月23日インタビュー 編集・撮影 toi編集舎 大越はじめ)