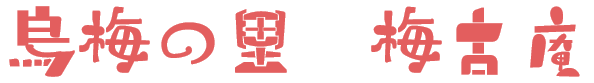2025/01/30 21:01

今年の梅古庵お食事処は2月8日〜3月31日まで営業し、お客様のお越しをお待ちしています。
今も昔も外国の評価や輸入品が好きな日本人ですが、梅も遣唐使によって唐から伝わりました。
当時お花見といえば梅。万葉集でも梅が沢山詠まれています。
万葉集で詠まれた植物
1萩 141首
2梅 118首
3松 79首
4橘 68首
5桜 50首
太宰帥(太宰府長官)の大伴旅人は梅花の宴を開催。31名の客人を自宅に招いて梅花の歌三十二首が詠まれます。序文は元号令和の由来になりました。
万葉集は当時の言語漢字で記されています。『うめ』の発音はあて字である万葉仮名『烏梅』と表記されます。
万葉集の『烏梅』は『うめ』の万葉仮名である事が通説ですが、日本文学者である国学院大学の辰巳正明教授はこの『烏梅』は当時伝わった薬としての烏梅に違いない、大伴旅人が梅花の宴で薬の烏梅を披露したのではないかと、令和元年に梅古庵を訪問し熱く語られました。
『大伴旅人』辰巳正明著 新典社
に詳しく書かれていますので興味ある方は参照下さい。
遣唐使と共に伝わった梅のお花見は、遣唐使の廃止によってその地位を桜に譲ります。唐の文化よりも国風文化が見直されお花見といえば日本古来の桜になりました。菅原道真公が好きだった梅は菅公の進言による遣唐使廃止によって人気に陰りが出る事になります。
平安京の内裏、紫宸殿もその頃、左近の梅から左近の桜に変わります。(右近の橘は今も変わらず)
烏梅は西暦1331年に月ヶ瀬に伝わりました。江戸時代後期には最盛期を迎え、烏梅を作る為に月ヶ瀬には梅の木が10万本植えられていました。
烏梅用の梅でしたが、五月川を背景にした満開の梅の景色が美しく、明治の文人墨客が多数訪れる観光地となります。大正11年には日本初の名勝にも指定されました。
紅花染めに使われた烏梅は化学染料の普及と共に需要は激減しました。梅の木も伐採され茶や桑畑に変わっていきます。月ヶ瀬の風景と観光事業が失われる事を嘆いた隣町の田中善助町長は月ヶ瀬梅渓保勝会を立ち上げ、月ヶ瀬の梅の伐採を止めました。その会は後に公益財団法人となり、現在も1万2千本の梅の木を管理されています。
五月川の瀬に映る梅と月が美しい月ヶ瀬。ぜひ今年の月ヶ瀬梅まつりにお越し頂き歴史と梅の香りに触れてみて下さい。
#月ヶ瀬
#梅まつり
#朝日新聞
#烏梅
#万葉集
#大伴旅人
#梅花の歌
#梅花の宴
#紫宸殿
#右近の橘
#左近の梅
#令和
#万葉仮名
#五月川
#梅古庵